2009年、登山者や観光客に人気の長野・岐阜県境の名峰「乗鞍岳」で、ツキノワグマによる襲撃事件が発生しました。
平和な山のイメージを覆す出来事に、多くの登山愛好家や地元民はもちろん全国的にセンセーショナルな事件となりました。
この記事では、乗鞍岳クマ襲撃事件の概要、ツキノワグマが暴走した原因、そしてその後に取られた対策について詳しく解説します。
乗鞍岳ツキノワグマ襲撃事故の概要(2009年9月19日)
発生日時・場所
2009年9月19日午後2時20分頃、岐阜県・長野県境にある標高2,702 m の「乗鞍岳 畳平バスターミナル」にて発生。連休中で、観光客や登山客が非常に多く訪れていた。
襲撃の経緯
- 大黒岳の中腹から1頭の雄のツキノワグマが全速力で駆け下り、ターミナル周辺にいた人々を次々と襲撃。
- まず68歳男性が肩から腹、左膝を傷つけられ重傷。続いて他の登山者も顔や頭などを集中的に襲われ、顔面骨折や歯・目を失う重傷者も。
- 現場の人々は石を投げたり、杖で応戦したりしたが、クマの興奮は収まらず、襲撃は連鎖的に続いた。
ターミナル建物内への侵入
- クマはバスターミナルの正面玄関ガラス扉を破り、館内に突入。避難していた観光客や職員を襲い、女性バス運転手が左耳を噛まれ重傷。
- 従業員らは消火器や椅子などを用いてクマを隔離。食堂と売店の間のシャッターを閉鎖し、クマを土産物店内に閉じ込めるなど、機転の利いた対応が見られた。
救護体制と終息
- 応急処置のために救護室が開設されたものの、標高が高く医師・看護師が常駐しない場所だったため、重傷者の対応は困難を極めた。救急車の到着も遅延した。
- 事件は約3時間40分後、猟友会により射殺され、クマは体長約130 cm、体重67 kg、年齢21歳の雄であった。死者はなく、10人が重軽傷を負った。
本来、ツキノワグマは人間を避ける臆病な性格とされています。しかし今回の事件では、クマが人に向かって突進するなど、通常では考えにくい攻撃的行動が見られました。
ツキノワグマが暴走した原因
一般的にツキノワグマが人を襲うケースにはいくつかの背景が考えられます。
① 餌不足によるストレス
その年のドングリや山の木の実が不作になると、クマは生き延びるために人里や登山道に近づきやすくなります。餌不足の状態は、クマの攻撃性を高める要因となります。
② 人間の行動による刺激
登山者の食べ物の匂いや、予期せぬ遭遇によってクマが興奮し、パニック状態に陥った可能性があります。特に背後から突然出会うケースは危険です。
③ 個体の性質
一部の若いオスや、人に慣れてしまった個体は攻撃的な行動を取ることがあります。
今回は餌は充分にあったといわれているので、興奮して攻撃的になった個体が人と接触し、その後、攻撃される人を守るためではあるけれど、継続的に刺激を受け続けた結果、さらに攻撃性をましてしまったと考えられています。
事件後に取られた対策
乗鞍岳での事件を受け、自治体や登山関係者は以下のような対策を強化しました。
- クマ出没情報の共有強化:登山口や山小屋に注意喚起の掲示を設置。
- クマ鈴・ラジオの携帯推奨:登山者が存在を知らせることで、不意の遭遇を避ける。
- ゴミや食べ物の管理徹底:匂いがクマを引き寄せないように、山小屋や休憩所でのルールを厳格化。
- 捕獲・駆除の検討:人に危害を加えた個体については、安全確保のために捕獲や駆除が実施される場合もあります。
まとめ
近年クマが市街地に降りてきて人を傷つける事件がおきており、乗鞍岳でのツキノワグマ襲撃事件が思い起こされました。
人が多くいるところにクマが入ってしまった場合には、大惨事になる可能性があります。
クマの目撃情報が報告されている地域では、撃退スプレーなど対策することが有効かもしれません。
最後までお読みくださりありがとうございました!



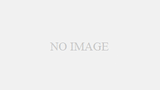
コメント