こんにちは!うさぎです。
2025年7月15日放送の『ザ!世界仰天ニュース』で「命脅かす食の危険!」をテーマに、実際に起きたボツリヌス菌食中毒を取り上げます。
東京都で「アユのいずし」を食べた女性がボツリヌス菌食中毒を発症した事例がありました。
さらに、近年ではレトルト食品と要冷蔵食品を間違えて保存したことが原因で発症したケースも報告されています。
食中毒といっても、お腹を下して・・・吐き気が・・・だけでは済まないのです。
筋肉麻痺して息ができなくなることも!
怖い!
この記事では、実際の事例の経緯や原因、発酵食品や市販食品での注意点について解説します。
気になる方は是非最後までご覧ください!
ボツリヌス菌とは?〜毒素の型と特徴〜
ボツリヌス菌は、土壌や川の泥の中など自然界に広く存在する嫌気性芽胞菌です。
酸素のない環境で増殖し、強力な神経毒素(ボツリヌストキシン)を産生します。
この毒素は食品由来の自然毒の中で最も強力で、極微量であっても命に関わる可能性があります。
潜伏期間は8〜36時間程度で、吐き気、嘔吐、視力障害、筋力低下、呼吸筋麻痺といった症状が現れます。
ボツリヌス毒素の型
ボツリヌス菌が産生する毒素は、抗原性の違いにより A型・B型・C型・D型・E型・F型・G型 に分類されています。
人間に食中毒や中毒症状を起こすのは主に以下の4つです。
| 型 | 主な発生源 | 特徴 |
|---|---|---|
| A型 | 土壌・野菜など | 比較的高温(温暖地)で発生。症状が重く、致死率が高い。 |
| B型 | 土壌・肉製品・野菜など | 温暖地に多い。A型より軽症で、回復も早い傾向。 |
| E型 | 河川や湖の泥・水産物(魚介類) | 低温環境でも増殖し、寒冷地や水産加工品に多い。 |
| F型 | 稀。土壌や環境中 | 非常に稀に報告。軽症の場合もあるが、まれに重症になる。 |
特にE型は、川魚や発酵魚類製品で多く発生しており、今回の「アユのいずし」でもこのE型が検出されました。低温環境でも増殖可能なため、冷蔵保存中の食品でも発生するリスクがあります。
治療は抗毒素血清の投与と呼吸管理が中心で、迅速な対応が重要です。
出典:東京都保健医療局
ボツリヌス菌食中毒の経緯と原因
東京都で発生したアユのいずし食中毒
患者は東京都杉並区在住の女性。知人からもらった自家製のアユのいずしを食べて発症しました。
日付ごとの経緯
- 2月12日
知人から「アユのいずし」を受け取る。 - 2月13日夕方
自宅でいずしを喫食。 - 2月14日朝
胃のむかつき、吐き気、午後には倦怠感・血圧低下。 - 2月14日夜
医療機関へ救急搬送される。 - 2月16日
瞳孔散大、呼吸不全となり人工呼吸器が必要に。 - 2月17日
担当医療機関から保健所に通報。
検査の結果、患者血清と残ったいずしからE型ボツリヌス毒素を検出し、食中毒と確定。 - 3月1日
杉並区杉並保健所は、本件を2月13日(日曜日)に自宅で喫食したアユのいずしを原因とする食中毒と断定。報道発表。
発酵食品のアユのいずしになぜボツリヌス菌が?
アユのいずし(飯ずし)とは?
「いずし(飯ずし)」は、東北や北海道などで食べられている伝統的な発酵食品で、米、麹、野菜と一緒に川魚を漬け込み発酵させたものです。
発酵により酸性度が高まり雑菌の繁殖が抑えられる仕組みですが、工程管理が悪いと酸性化が遅れ、酸素のない環境でボツリヌス菌が増えてしまいます。
ボツリヌス菌が発生した理由
- 酸性度が十分に下がらなかった
- 塩分や麹が不足していた
- 熟成中の温度が高かった
- 器具や材料が汚染されていた
こうした条件が重なると、毒素が生成される危険性があります。
本来いずしは乳酸発酵によって酸性化することで保存性を高めますが、今回は酸性化が不十分だったため、酸素の少ない状態でボツリヌス菌が増殖し、毒素を産生したと考えられます。
発酵食品以外でも!レトルトとチルドを間違えてボツリヌス菌食中毒
発酵食品以外にも、ボツリヌス菌食中毒は発生しています。
近年の2つの事例を紹介します。
1. レトルトと間違えた要冷蔵スープ
新潟市で、購入した要冷蔵の密封スープをレトルト食品と勘違いし、常温で2ヶ月保存した後に喫食した女性が食中毒を発症しました。
喫食の翌日から、眼のチカチカ感、食べ物の飲み込みにくさ、言葉が発しにくいといった症状を自覚し、その後、全身の麻痺症状が現れました。
患者の血清と便からC型ボツリヌス毒素が検出され、常温保存で増殖・毒素産生したと考えられました。
出典:大阪健康安全基盤研究所
2. ハヤシライスソースで発症
別の事例として、以前「ザ!世界仰天ニュース」でも紹介されましたが、市販のハヤシライスソース(チルド食品)をレトルト食品と勘違いし、常温で約9日間保存してしまったケースです。
患者は喫食後に視力障害やふらつき、呼吸困難など典型的なボツリヌス中毒症状を訴えました。
これは、嫌気性環境でボツリヌス菌が増殖し、強力な神経毒素が生成されたことによるものです。
患者の女の子は病院で抗毒素治療を受け、1年という長い時間がかかりましたが、幸い回復しました。
まとめ
アユのいずし、密封スープ、煮魚と、ボツリヌス菌食中毒の事例は決して珍しくありません。
共通しているのは「酸素がない状態で、適切な酸性度・温度管理がされずに増殖した」という点です。
注意すべきポイント
✅ 自家製発酵食品は十分な塩分・麹で酸性化を確認する
✅ 発酵食品は必ず冷蔵で保存し、異臭・異変があれば食べない
✅ 市販品の「要冷蔵」「要冷凍」の表示を必ず守る
✅ 密封状態の食品は長期保存しない
✅ 体調不良を感じたらすぐ医療機関を受診する
とはいえ、家庭では十分な塩分なのか発行が十分なのかの判断は難しいところ。
ですから、この事件を受けていずしを作る文化のある地域では、家庭でつくるいずしについて注意喚起が行われています。
①つくらない、②食べない、③人にあげない
出典:福島県南会津保健所
伝統食品や市販食品は、正しい作り方・保存方法を守れば安全に楽しめます。
大切なのは、正しい知識とちょっとした注意です。安全に美味しさを楽しみましょう。
最後までお読みくださりありがとうございました。


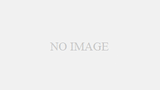

コメント